MEMBER's COLUMN
蚊が減ってトンボが増えた? 温暖化による生態系の変化
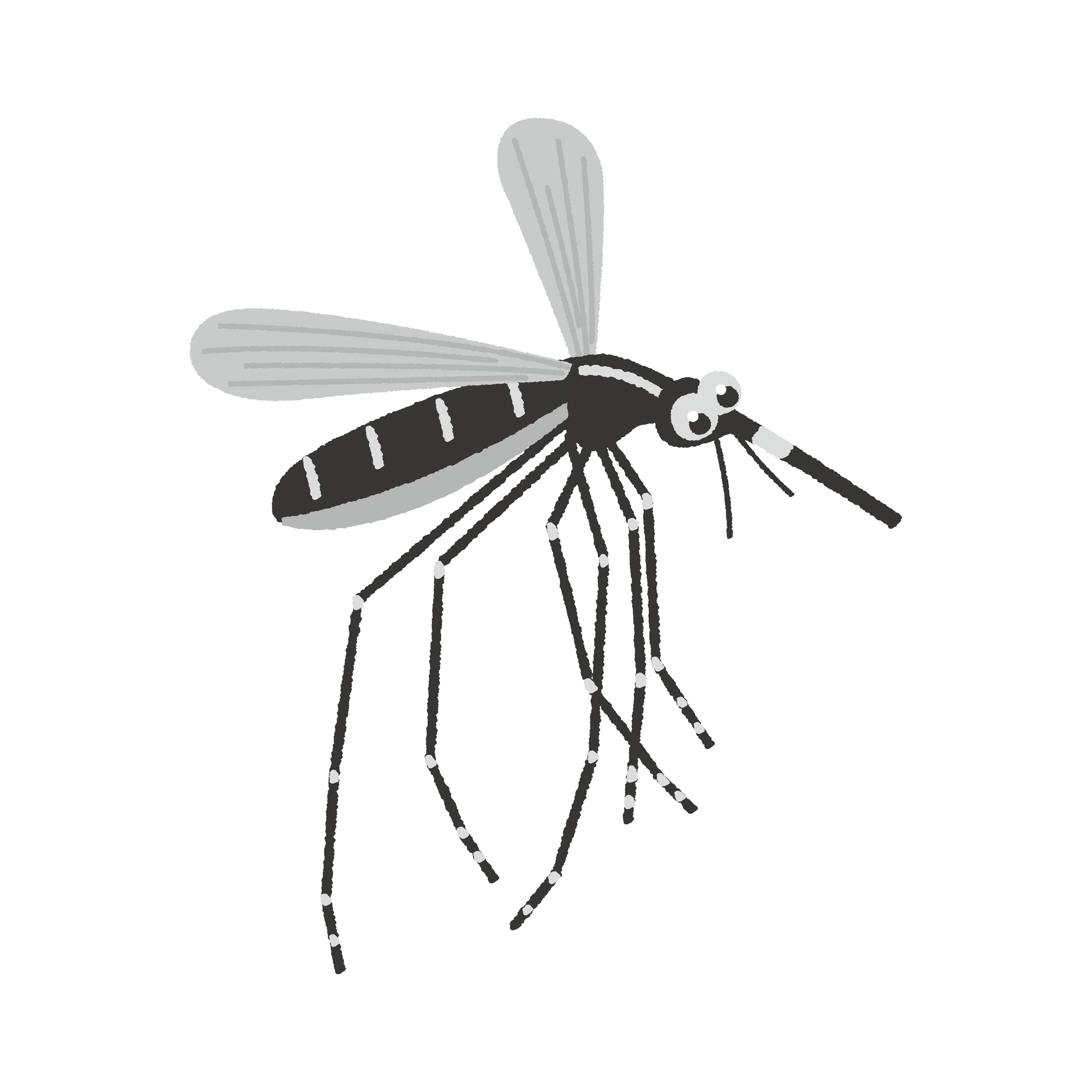
夏の猛暑は蚊の活動にも影響
2025年夏の日本の平均気温は平年を大きく上回り、統計開始以来最も暑い夏となりました。記録的な猛暑日が続く昨今の夏、一部では「蚊を見なくなった」という声が広まっています。
殺虫剤メーカーでは、シーズンで最も売れ行きが高いと思われる7月、8月の売上が減少しているという報告がありました。
実は、都市部に多く生息するヒトスジシマカは、35℃を超える猛暑日には活動が鈍くなり、産卵や発育に影響が出ることが分かっています。
夏に猛威を振るうイメージがある蚊の活動は、近年の異常な暑さによって変化しているのです。
殺虫剤メーカーでは、シーズンで最も売れ行きが高いと思われる7月、8月の売上が減少しているという報告がありました。
実は、都市部に多く生息するヒトスジシマカは、35℃を超える猛暑日には活動が鈍くなり、産卵や発育に影響が出ることが分かっています。
夏に猛威を振るうイメージがある蚊の活動は、近年の異常な暑さによって変化しているのです。

蚊が減ってトンボが増えた?
「蚊を見なくなった」一方で「やけにトンボを目にする」といった声もささやかれています。
夏の終わりから秋にかけて増加するアキアカネやシオカラトンボなどは、蚊を捕食する種類です。一日数百匹もの蚊やアブを捕食するといわれています。また、トンボの幼虫であるヤゴは、蚊の幼虫であるボウフラを捕食します。
35℃以上の猛暑によって一定の数を減らしたり、活動が鈍ったりした蚊やボウフラが、気温の低下とともに活動を再開しようとした直後に、トンボやヤゴによって捕食されたということが考えられます。
日本国内のトンボの数は、全体として減少傾向にあるため、この一連の動きが、結果として「蚊が減り、トンボが増えた」という現象として体感的に認識されているのかもしれません。
夏の終わりから秋にかけて増加するアキアカネやシオカラトンボなどは、蚊を捕食する種類です。一日数百匹もの蚊やアブを捕食するといわれています。また、トンボの幼虫であるヤゴは、蚊の幼虫であるボウフラを捕食します。
35℃以上の猛暑によって一定の数を減らしたり、活動が鈍ったりした蚊やボウフラが、気温の低下とともに活動を再開しようとした直後に、トンボやヤゴによって捕食されたということが考えられます。
日本国内のトンボの数は、全体として減少傾向にあるため、この一連の動きが、結果として「蚊が減り、トンボが増えた」という現象として体感的に認識されているのかもしれません。


また、温暖化が進行する中で、暖かい地域に生息していたトンボなどが分布域を北へ拡大させている例も報告されています。
特定の種が気候変動に適応して数を増やしたり、生息地を広げたりしていることから、トンボを目にする機会自体が増えた可能性も考えられます。
特定の種が気候変動に適応して数を増やしたり、生息地を広げたりしていることから、トンボを目にする機会自体が増えた可能性も考えられます。
なぜ猛暑日が増えたのか
気象庁は2007年に、日最高気温が35℃以上の日を「猛暑日」と定義しました。2018年には7日以上の猛暑日を記録し、過去最多を更新しています。またこの年には、観測を開始してからの最高気温となる41.1℃も記録されました。この年以降、私たちは夏場になると、生命の危険を脅かすような暑さが襲ってくるという危機感を持ち始めるようになりました。
この2018年の異常気象は日本国内だけのものではなく、世界各地で多くの被害を出し、問題視されました。気象研究所や東京大学などとの共同研究の結果、これらの猛暑は地球温暖化が関係しているということが明らかになっています。
この2018年の異常気象は日本国内だけのものではなく、世界各地で多くの被害を出し、問題視されました。気象研究所や東京大学などとの共同研究の結果、これらの猛暑は地球温暖化が関係しているということが明らかになっています。
地球温暖化はなぜ起こるのか
地球には、地表の熱を適度な温度に保つ「温室効果」という仕組みがあります。
しかし、産業革命以来、人間が石炭や石油といった化石燃料を使いすぎたために、「温室効果ガス」が大量に増え、地球が持っている熱のバランスが崩れてしまいました。
温室効果ガスが増加したことによって、地球から宇宙へ放出されるはずの熱が、大気中に吸収され、再び地表に戻ってくることを繰り返したことで温室効果がこれまでより強まり、地球全体の平均気温が上昇してしまっているのです。
しかし、産業革命以来、人間が石炭や石油といった化石燃料を使いすぎたために、「温室効果ガス」が大量に増え、地球が持っている熱のバランスが崩れてしまいました。
温室効果ガスが増加したことによって、地球から宇宙へ放出されるはずの熱が、大気中に吸収され、再び地表に戻ってくることを繰り返したことで温室効果がこれまでより強まり、地球全体の平均気温が上昇してしまっているのです。

温室効果ガスを減らすためにできること
温室効果ガスが発生する最大の原因は化石燃料の燃焼によるものです。実は、プラスチックを製造する過程においても二酸化炭素は発生します。
プラスチックは、原料の調達から製品化に至るまでの各工程において、大量の化石燃料が消費されます。温室効果ガスを削減するためには、その主な原因となる二酸化炭素を減らす必要があり、結果としてプラスチックの生産量および使用量を削減することが求められます。
そのための具体的な取り組みとして、繰り返し使える容器の活用などに加え、使用済みプラスチックを再び原料として利用する「マテリアルリサイクル」や、プラスチックを化学的に分解し、資源として再利用する「ケミカルリサイクル」といった方法を積極的に取り入れていくことが必要とされてくるでしょう。
プラスチックは、原料の調達から製品化に至るまでの各工程において、大量の化石燃料が消費されます。温室効果ガスを削減するためには、その主な原因となる二酸化炭素を減らす必要があり、結果としてプラスチックの生産量および使用量を削減することが求められます。
そのための具体的な取り組みとして、繰り返し使える容器の活用などに加え、使用済みプラスチックを再び原料として利用する「マテリアルリサイクル」や、プラスチックを化学的に分解し、資源として再利用する「ケミカルリサイクル」といった方法を積極的に取り入れていくことが必要とされてくるでしょう。
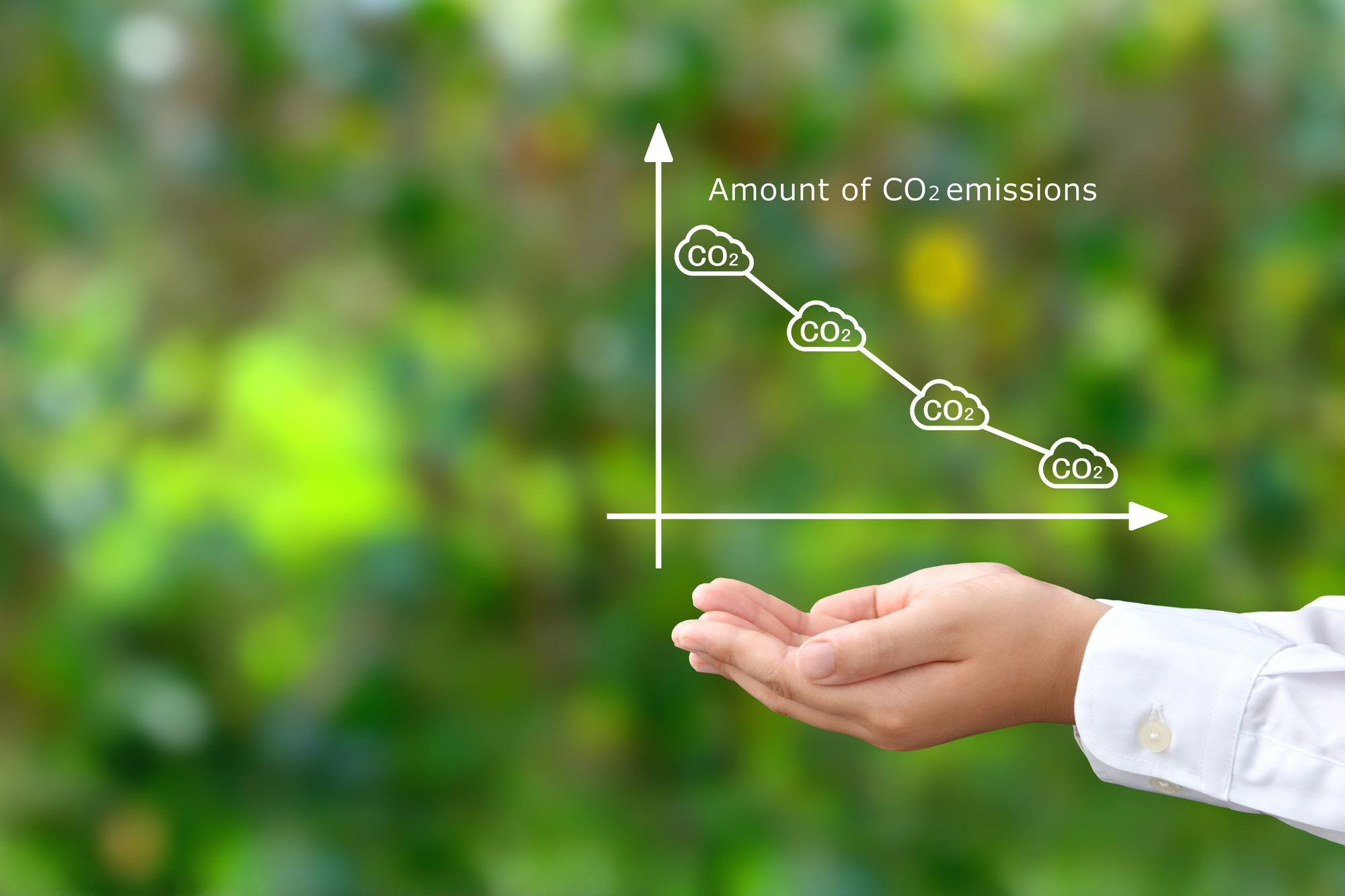
プラスチックを製造することで発生する温室効果ガス。その影響は、夏の猛暑や自然生物の行動の変化など、私たちの日常のすぐそこにまで姿を現しています。何気ない日々の営みの中にも、環境問題の影が潜んでいます。自然との共存を図りながら共に歩みを進めていくために、私たちは「今、何ができるのか」を深く考えていく必要があります。