MEMBER's COLUMN
「脱プラスチック」って、いつから?どんなきっかけ?

プラスチックの歴史
私たちの暮らしにすっかりなじんでいるプラスチック。
「脱プラスチック」という言葉は、今やよく耳にすることがあると思います。
一体、いつから「脱プラスチック」は始まったのでしょうか?
まずは、プラスチックの歴史を簡単に振り返ってみると、そのはじまりは、意外と昔にさかのぼります。
最初に人工的に作られたプラスチックは、1800年代後半のこと。
当時は、象牙やべっ甲などの天然素材が不足してきたことから、その代わりになる素材をつくろうと考えられました。
そうして生まれたのが、櫛やボタン、ビリヤードの球などに使われた硬いプラスチックです。
「脱プラスチック」という言葉は、今やよく耳にすることがあると思います。
一体、いつから「脱プラスチック」は始まったのでしょうか?
まずは、プラスチックの歴史を簡単に振り返ってみると、そのはじまりは、意外と昔にさかのぼります。
最初に人工的に作られたプラスチックは、1800年代後半のこと。
当時は、象牙やべっ甲などの天然素材が不足してきたことから、その代わりになる素材をつくろうと考えられました。
そうして生まれたのが、櫛やボタン、ビリヤードの球などに使われた硬いプラスチックです。


1900年代に入ると、化学的に合成された新しいタイプのプラスチックが登場し、軽くて丈夫で、加工しやすい「夢の素材」として広がっていきます。
そして1950年代からは大量生産が始まり、食品容器や袋、日用品など、生活のあらゆる場面にプラスチックが使われるようになりました。
そして1950年代からは大量生産が始まり、食品容器や袋、日用品など、生活のあらゆる場面にプラスチックが使われるようになりました。

このプラスチックは、ほとんどが石油から得られる「ナフサ」を化学的に合成して作られます。
ナフサを加熱分解して得られるエチレンやプロピレンなどの小さな分子を、さらに化学的に結合させることで高分子のプラスチックにします。
子供のおもちゃから、車、工業機械、デジタルデバイス、生活の中の多くの場所に、このプラスチックが使用されています。
ナフサを加熱分解して得られるエチレンやプロピレンなどの小さな分子を、さらに化学的に結合させることで高分子のプラスチックにします。
子供のおもちゃから、車、工業機械、デジタルデバイス、生活の中の多くの場所に、このプラスチックが使用されています。

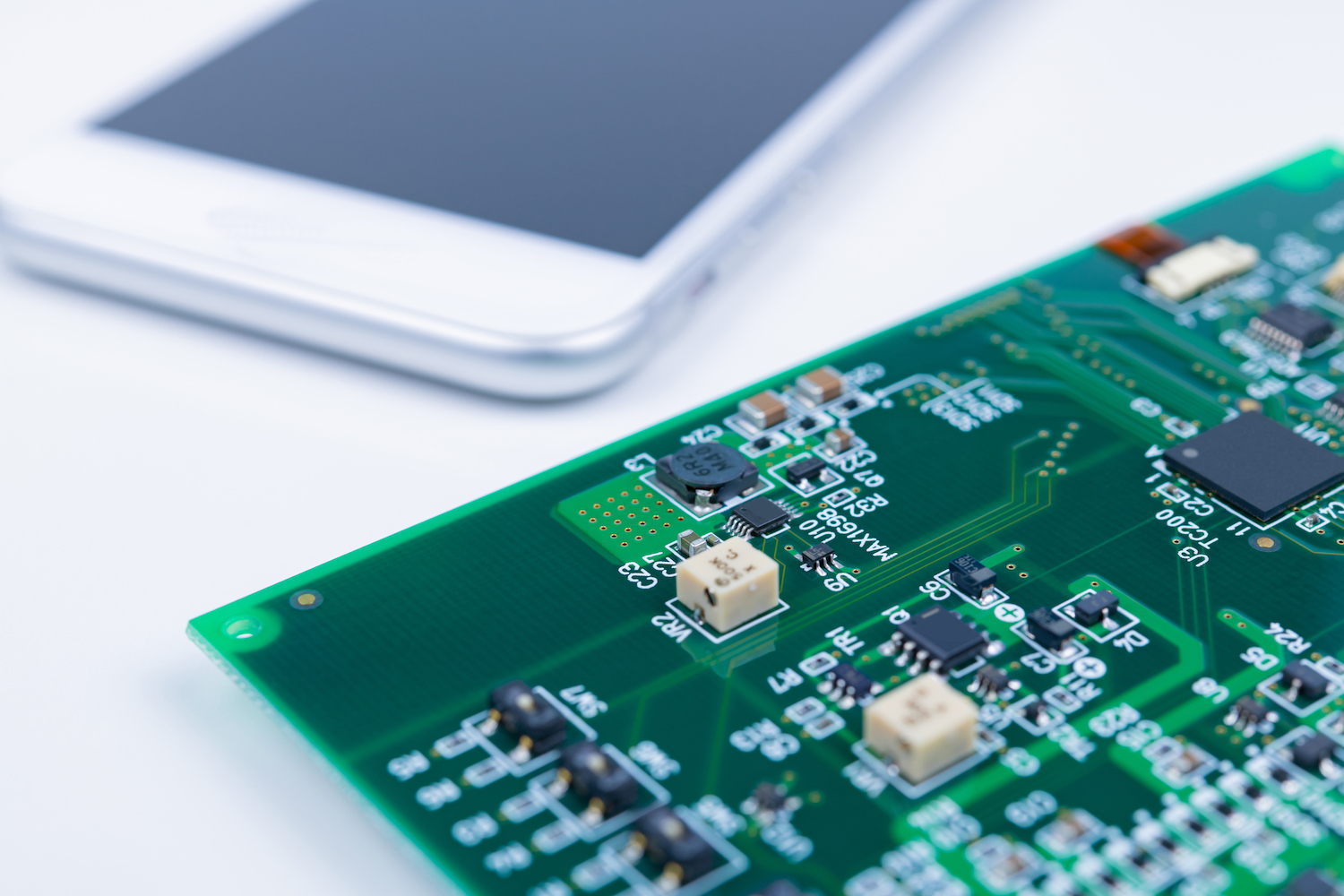
脱プラスチックのはじまり
しかしその一方で、「便利さ」の裏にある課題も少しずつ見えてきます。
プラスチックは丈夫で、自然に戻るために長い時間がかかるため、ごみとして廃棄された後も、人間の暮らしの足跡として環境に残り続けてしまうのです。
プラスチックは丈夫で、自然に戻るために長い時間がかかるため、ごみとして廃棄された後も、人間の暮らしの足跡として環境に残り続けてしまうのです。

1980年代頃からは、ごみ問題が注目されるようになり、リサイクルや分別回収が進みますが、それでもプラスチックごみの量は減らず、2000年代には、海に流れ出たプラスチックが魚やウミガメなどの生き物に与える影響が大きな問題になりました。

特に、5ミリ以下の小さなプラスチック片「マイクロプラスチック」が生態系や人間の健康にも関わる可能性があると分かり、世界中で大きな関心を集めます。
2010年代後半から、「脱プラスチック」という言葉が使われ始めました。
きっかけとなったのは、大量に使われていた使い捨てのストローや容器をやめようという動き。
みなさんの知っているカフェやファストフードでもストローが紙になったことは記憶に新しいはずです。
環境配慮を重視した企業、団体が次々と対策を発表し、ネットやニュースでも頻繁に取り上げられるようになりました。
そして今、「脱プラスチック」は一部の人の特別な取り組みではなく、社会全体で考える大きなテーマになっています。
レジ袋が有料になったり、繰り返し使える容器が増えたりと、私たちの暮らしの中にも少しずつ変化が広がっています。
そして今、「脱プラスチック」は一部の人の特別な取り組みではなく、社会全体で考える大きなテーマになっています。
レジ袋が有料になったり、繰り返し使える容器が増えたりと、私たちの暮らしの中にも少しずつ変化が広がっています。
プラスチックは悪?
ただし、「プラスチック=悪」と単純に言い切れるわけではありません。
たとえば、食品を清潔に安全に届けるための包装材として、プラスチックはとても大きな役割を果たしています。
衛生面や保存性に優れており、食品ロスを減らすことにもつながっています。
また、医療用の器具や子どものおもちゃ、スマートフォンやパソコンといった身近な製品にも、プラスチックは欠かせません。
つまり私たちは今、「プラスチックの便利さに助けられている現実」と、「環境への影響を減らしたいという願い」の間で、どうバランスを取っていくかを問われているのです。
たとえば、食品を清潔に安全に届けるための包装材として、プラスチックはとても大きな役割を果たしています。
衛生面や保存性に優れており、食品ロスを減らすことにもつながっています。
また、医療用の器具や子どものおもちゃ、スマートフォンやパソコンといった身近な製品にも、プラスチックは欠かせません。
つまり私たちは今、「プラスチックの便利さに助けられている現実」と、「環境への影響を減らしたいという願い」の間で、どうバランスを取っていくかを問われているのです。

プラスチックそのものをすべてなくすのではなく、本当に必要な場面とそうでない場面を見きわめて、上手につきあっていくこと。
このプロジェクトでも、様々な切り口から「プラスチック」を考えていきます。
このプロジェクトでも、様々な切り口から「プラスチック」を考えていきます。